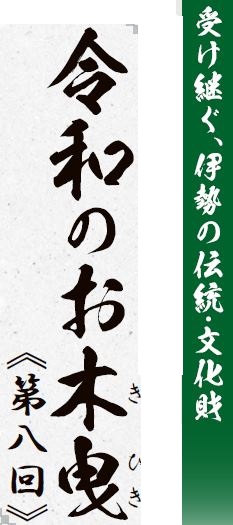
■木曽から伊勢へ御用材で託される思い
神宮式年遷宮に使用する御用材は、江戸時代から約300年にわたり木曽より伐り出され、伊勢まで大切に運ばれてきました。また、時代の移り変わりとともに、運搬方法は水運から陸運へと変わりました。御神体をお納めする器をつくるための御用材である「御樋代木(みひしろぎ)」は、前回の第62回神宮式年遷宮では、新車のトラックにて奉搬ルートの長野、岐阜、愛知、三重の各地の沿道で盛大な歓迎を受けながら、伊勢に到着しました。
御樋代木の伐採は、伝統技法の「三ツ緒伐(おぎ)り(三ツ紐(ひも)伐り・三ツ伐り)」と呼ばれる方法で幹の3方向から手斧で木を彫り、3カ所を残して「ツル」を作りながら内部をくり抜いて伐採します。古くから伝わるこの技法は、伐倒方向が正確で木が倒れる際の割れも少なく、安全に伐採することができますが、樹齢300年以上の木を手斧で伐ることから、木の特性を見極め、倒す方向を読みながら伐採するなど、長年の経験と技術が必要です。
今回は、この伝統技法を継承し、次世代へとつなげる長野県上松町の三ツ紐伐り保存会・伊勢神宮木曽奉賛会と、岐阜県中津川市裏木曽三ツ伐り保存会の皆さんにその思いを聞きました。
長野県上松町の杣頭(そまがしら)の橋本さんは、「斧で木を伐るには風の動きや枝の入り具合、木がどちらに寝たがっているか※を見極めないといけません。」と自然と対話しながら大切な木を丁寧に伐採しています。
岐阜県中津川市の杣頭の鈴木さんは、「斧で伐るのは普段できない特別なこと。木によって成長は違うし、同じようにはいきません。その加減を体が覚えるよう、経験が大事です。」と教えてくれました。森林文化や伝統技法を継承することで伊勢への思いを深め、次の世代へとつなげるため一体となり保存・継承に取り組んでいます。
※寝かす…木を伐り倒すこと。
■思いを受け止め御用材を奉曳
前回の第62回神宮式年遷宮では平成17年6月に、御樋代木の奉曳が行われました。
川曳では、揃いの黒はっぴを着た曳き手が力強く木遣りを唄いながら、五十鈴川の浦田橋下流から奉曳し、風日祈宮橋(かざひのみのみやばし)のたもとで曳き上げました。一方陸曳では、度会橋から外宮北御門までを奉曳車のワン鳴りを響かせながら「エンヤ!」の掛け声で、心一つに奉曳しました。
御樋代木には上松町や、中津川市の人々が何代にもわたり、大切に守ってきた樹齢300年以上の檜(ひのき)が使用されます。木曽から大切に育て、歓迎を受けながら運ばれる御用材と託された思いを受け継ぎ、心を込めて奉曳しました。
第63回神宮式年遷宮でも、御用材を通して伝統や思いをつなげていきます。
※伊勢御遷宮委員会発行「令和のお木曳」第2・3号から一部内容を再編しています。
お木曳などについて詳しくは、伊勢御遷宮委員会のホームページをご覧ください。
問合せ:伊勢御遷宮委員会事務局〔伊勢商工会議所・5階〕
【電話】25–5215【FAX】63–5339
※お木曳の歴史については…文化政策課【電話】22–7884【FAX】21–0424
<この記事についてアンケートにご協力ください。>

