6月ともなると夏の日差しは一層厳しく、お花を眺めながら散歩するだけでも、時折日陰で休みたくなります。日陰というと植物の育ちづらい場所のようなイメージがあるけれども、元来日本は山間渓谷の多い国土のためか、日陰を好む植物がた~くさんあります。「うん、茶席に向かう露地に植えられているものはその代表だよね?」その通り!うまいこと言いますね。その中の一つがこれから初秋に向かって咲くギボウシです。
ギボウシは中国四川省から日本にかけての温帯地域の山間渓谷に生息するキジカクシ科ギボウシ属に含まれる種(しゅ)の総称で、日本には多くの固有種があります。晩春から初夏に葉が展開し、その後に花が咲き始めます。花の色は品種によって違いますが白から紫色の色幅に収まり、品種によっては良い香りが楽しめます。しかし、ギボウシの楽しみは花よりも、葉の姿で、放射状に平たく広がるその姿には趣が感じられます。葉の大きさは小葉のものから大葉のものまで、葉の色は薄黄色から濃緑色さらに銀葉のものもあり、また、品種によって葉に様々な斑模様が入ります。暑いさ中、日陰で一息つきながら楽しめる、日本の夏にふさわしいお花ですね。
ギボウシの名称は、花の蕾の形が旧日本橋欄干(らんかん)等の頭部に備えられた擬宝珠(ぎぼし)に似ていることから、そう呼ばれるようになったようですが、『訓蒙図彙(きんもうずい)』(寛文6年、中村惕斎(なかむらてきさい))巻二十-草花の部には「玉簪(ぎょくさん)俗云ぎ本うし玉簪花(ぞくにいうぎぼうしぎょくさんくわ)一名白鶴仙(いちめいはくくわくせん)」とあり、江戸初期以前の正式名称は玉簪(ぎょくさん)であったことがわかります。玉簪はもともと中国名で、現代中国でもギボウシの正式名称は玉簪(ユーザン)(翡翠(ひすい)のかんざし)です。玉簪の名称は、伝説によると、漢の武帝が愛妾(あいしょう)の李夫人の髪にこの花を挿し、その後宮中の女官がこれをまねて、この花を翡翠のかんざしの様に髪に飾ることが流行り、こう呼ばれるようになったと言われています。「日本に固有種がたくさんあっても中国の名前で呼ばれてたんだね~?」そうですね、江戸初期の時点で、文化レベルでは日本がリードしている面が多々あったと思いますが、やはり本草学の分野では日本は中国を手本にしていたため、これもそれに従ったのでしょうね?
おっと、いつの間にか字数がいっぱい!ではギボウシのお話はこれにて終了。皆さん熱中症にお気をつけ下さいね~!
執筆 愛知豊明花き流通協同組合 理事長 永田晶彦
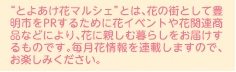
<この記事についてアンケートにご協力ください。>

