~グローカルの源流~
最終回は、グローカルの源流とも言える幕末の子ども達の姿からグローカルCITYである下田の未来についてお伝えします。
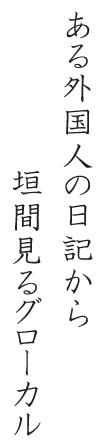
1855年に米海軍の測量隊の一員として下田や函館など日本各地を調査したアレクサンダー・ハバーシャムは、「マイ・ラスト・クルーズ一八五五年アメリカ海軍北太平洋測量艦隊日本航海・琉球・下田・箱館・蝦夷地滞在記」という滞在記を残し、開港直後の下田の様子や情景、人々とのふれあいを一兵卒ならではのリアリティ溢れる筆致で描いています。
彼が下田に滞在した1855年はペリー来航の一年後、安政の地震から約半年後です。
そのときの下田は、復興後、もしくは復興最中でした。
新築の家々の構造、欠乏所やお風呂での外国人とのやりとりなど、感情のこもった細かい描写は公的な資料にはなかなか見られないものです。
その中でも、彼が下田港から柿崎へボートで到着したとき、子どもたちが彼らを出迎えた描写は、下田が開港場として獲得した、かけがえのないグローカルの萌芽を感じさせます。
「柿崎との間の海岸に上陸し、浜辺沿いに柿崎のはずれまで歩いた。すると大変な数の子供たち、可愛い少女たちが我々を歓迎しに来たのは驚きの始まりだった。外国人を見ようと家から飛び出し、行く手にずらりと並んで、頭上には奇抜な絵が描かれた傘をさし、足下は履きにくそうな竹馬に似たサンダル〔下駄〕を履いている。ざっと見たところ、子供たちは好奇心いっぱいであるとともに、かなり小生意気そうに見えるが、概して態度には大胆さが目立つ」
「この特別な地方の人々は、これまでにアメリカ人を十分に見ており、明らかにペリー提督の二度の訪問の間に好意的な知識を得てきており、我々を見ても恐れる様子はない。」、「両手を上げてHow do you do?とか、Ohio!と挨拶し、」、「我々の言語の二、三の言葉を知ろうとする大変な熱心さを示すのである」
「特に私が覚えている少年は、ちょっとの間に十までの数字を数えるのを覚えた。次の日に砂浜で、尖った棒を手にしたかれを見つけると、少年はその棒でone,two,threeなどと丁寧に書いていた。こうして一か月でも叩き込めば、多くの坊主頭の少年たちも同様に、素早く、正確に覚えることだろう」
「まだ子供の体格と、明るく輝く眼を見ると、日本人の頭脳が高度の思考力をもっていることが分かり始めた」
◆引用書籍
著者:アレクサンダー・ハバーシャム
編訳:山本 秀峰(やまもとしゅうほう)
タイトル:『マイ・ラスト・クルーズ -一八五五年アメリカ海軍北太平洋測量艦隊日本航海・琉球・下田・箱館・蝦夷地滞在記-』
出版社:露蘭堂、2023年11月
引用頁:37、38頁
※引用文傍点は下田市にて追記
※市立図書館で貸出可
◆同じ地点での特異点
一般的には「黒船来航」というイメージは、一般住民は恐ろしくて戸を閉ざし、震えていた、というような先入観があるかもしれません。
もちろんそういった態度は時代によっては史実だったかもしれませんが、この日記から見えるペリー来航から一年後の下田では、外国人にとても友好的で、子ども達は外国語に興味を持ち、外国人との交流に積極的な世界だったということです。
この心温かな情景のほんの数年前、吉田松陰は同じ柿崎の地から米国船への乗船を試みますが、失敗に終わります。
それはただの失敗では無く、そのことが大きなきっかけとなって、彼は故郷萩で多くの門下生を持ち、その中から数々の偉人を輩出しました。
同じ砂浜でありながら、ほんの少しのタイミングで気兼ねなく外国人に触れ合えた人とそうでない人ができてしまうのも、幕末という大きな転換点ならではの出来事です。

下田の個性の最たるものとして、幕末開港の歴史があります。
歴史は常に過去から現在、未来へと流れていきます。
幕末の下田が開港場としての役割を果たしたきっかけは、江戸初期に江戸大坂間の中継港として活躍した歴史がありました。
そして、幕末開港期に始まった国際交流の歴史は、黒船祭や日露交流、姉妹都市交流など幅広い要素を包みこみ、現在につながってきています。
下田市は「グローバリズム(国際性)」と「ローカリズム(地域性)」を組み合わせた「グローカルCITYプロジェクト」を推進しています。
これはこれまでの下田の歴史と国際交流をまちづくりへ更に反映させていくことで、この先の未来につなげていく取組です。
今後10年、20年、さらに多くの年月が過ぎたとき、私たちの生きている現在も、幕末開港を一つの通過点とした歴史の一部となります。
開港170周年という節目に、下田の歴史を、そして未来を考えるきっかけにしていただければ幸いです。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>

