- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県山添村
- 広報紙名 : 広報やまぞえ 令和7年3月号
■大川(おおこ)遺跡・カントリーパーク大川
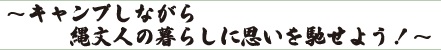
場所:山添村大字中峰山(ちゅうむざん)
年代:縄文時代
説明:縄文時代早期から晩期の集落遺跡で、たて穴式住居跡や集石炉(しゅうせきろ)や底がとがった深い鉢(はち)のような形で、表面に模様を付けた「押型文土器(おしかたもんどき)」など多数発掘されました。大川遺跡から発掘された土器は、「大川式土器(おおこしきどき)」と名付けられ、奈良県立橿原考古学研究所博物館(ならけんりつかしはらこうこがくけんきゅうしょはくぶつかん)で展示されています。また、出土した遺物は、山添村歴史民族資料館にも展示されています。更に、たて穴式住居やパネル展示(カントリーパーク内の管理棟)では縄文時代の生活がうかがえます。
現在、近くを流れる「名張川(なばりがわ)」では、魚釣り、カントリーパーク内では、キャンプ・バーベキュー、また、子どもに人気の「ローラー滑り台」があり、子どもから大人まで楽しむことができます。
■十一面観音菩薩立像(じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう)

場所:山添村大字広代(ひろだい)
年代:平安時代後期
説明:制作年代等は不明ですが、その作風から平安時代後期の作と考えられています。平安時代の優秀な仏師の作と推定され、鼻柱(はなばしら)、唇、耳、顔、肩面などに当時の典型的な作風が表れていて、後世に塗られた彩りがなければ県文化財の指定価値があると考えられています。この仏像は広代の大久保(おおくぼ)氏の祖先が江戸より持ち帰って家の前の山に祠(ほこら)を設け祭っていたと伝えられており、貞亨(じょうきょう)元年9月18日広代村に献上されたものです。厨子(ずし)の両扉には、本尊を中心に美如龍王(みにょりゅうおう)と赤誠童子(せきせいどうじ)の図が描かれ、完全な十一面観音三尊となっています。
この仏像は観音堂秘仏とされ、年2回、1月5日の「オコナイ」と旧の8月17日観音会式に開帳されています。
