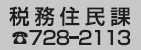- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県久米南町
- 広報紙名 : 広報くめなん 令和6年11月号
■1月1日までに固定資産の確認を
固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。
固定資産の評価は、固定資産評価基準に基づいて行い、決定した価格などは、固定資産の課税台帳に登録します。
この価格について、適正であるかどうかを他の土地・家屋と比較ができるようにするため、毎年4月の1カ月間、縦覧期間を設けています。縦覧は無料です。
固定資産に関する届け出には、添付書類が必要なものがあります。また、現地確認などが必要になるため、届け出やご相談はお早めにお願いします。-
▽土地
土地の固定資産税は、登記簿か土地課税台帳に所有者として登記・登録されている人が納めます。
土地の地目は約30種類あります。一般的に評価が高い順から宅地、田、畑、雑種地、山林、原野の6種類が代表的な課税地目です。登記上の地目ではなく、現状の地目で課税しますので、課税地目の変更(田から原野になったなど)を希望する人は、税務住民課へ届け出をお願いします。
土地に関する固定資産税は、土地課税台帳により算定します。土地課税台帳には、皆さんが所有する土地について、所有者、地目、地積、登記年月日が記載されています。所有権移転、分筆や合筆、地目変更や地籍変更など土地の異動があった場合は、法務局からの「登記済通知書」に基づき、台帳を整理しています。
▽家屋
家屋の固定資産税は、登記簿か家屋課税台帳に所有者として登記・登録されている人が納めます。
住居や車庫など建物の新築・増改築・取り壊しを行った場合や未登記家屋の所有者を変更する場合は、税務住民課へ届け出が必要です。届け出がないと課税漏れとなり、さかのぼって税金を納めたり、取り壊した家屋に課税されることがあります。
また、登記している家屋を取り壊した場合や所有者を変更した場合は、法務局での手続きが必要です。
▽償却資産
1月1日現在で、久米南町内に事業用資産を所有している個人や法人が対象となります。
個人で家屋の屋根などに発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となるため対象になります。
●農業用資産は必要経費の対象です
農業所得の申告に向けて収支計算を行う際に、田畑など農業用資産にかかる固定資産税が、租税公課として必要経費の対象になります。
固定資産税納税通知書に同封している課税明細書は、申告時期まで大切に保管して収支計算に活用してください。
●所有権の相続は必ず役場に連絡を
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が実施されました。
土地や家屋などの所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記が必要です。また、未登記家屋がある場合は、税務住民課で名義変更の手続きが必要です。
所有権を相続された人へ今後の納税通知書を送付しますので、あらかじめ固定資産の明細や納付方法(納付書払いか口座振替)などの確認をお願いします。また、相続放棄されている場合やその予定がある場合には、必ず税務住民課まで連絡をお願いします。
口座振替をご希望の場合は、手続きが必要です。取り扱い金融機関は、中国銀行、トマト銀行、晴れの国岡山農協、津山信用金庫、ゆうちょ銀行です。手続きはお早めにお願いします。
■今から準備 農業所得の申告
毎年1月1日から12月31日までの1年間に農業を営み、農作物の販売収入があった人は、申告をする必要があります。
農業所得の計算は、1年間の収入金額や必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
所得申告の時期が近くなってからでは、1年間の収入や支出を整理するのは大変です。今から収支に関する領収書類を項目ごとに整理、記録しておきましょう。月別集計記入表が必要な人は、税務住民課までお越しください。
※事業として行っていない農業(自家用の飯米や家庭菜園の場合)については、申告することができません。
▽帳簿書類の作成を必ず!
事業所得(農業所得)と認められるためには、営利を目的に継続した事業が行われており、帳簿書類が必ず保存されていることが最低条件です。申告相談の際には、必ず帳簿を作成してご来場ください。
▽減価償却について
減価償却とは、事業などの業務のために用いられる資産の価値が、時の経過などによって減っていくと考え、その使用期間に応じ、費用として分配する手法です。
主な減価償却資産の耐用年数:
・トラクター、耕運機、田植機、コンバインなど…7年
・軽トラック…4年
▽収入金額
販売金額:本年中の販売金額を記入します。なお、販売後、実際に代金を受け取っていない場合でも、本年中に販売したものは、すべて本年分の販売金額になります。
・米の販売金額(農協への委託販売収入)
・自主流通米の精算金(入金があった年に、その入金額を計上)
・青空市などの出荷売上金額
・ワラやもみ殻などの副産物の販売
・くず米やもち米など
家事消費・事業消費:収穫した時の生産者販売価格により計算します。
・米の自家消費(保有米・縁故米)
・野菜の自家消費
・現物支給による米などの事業消費(雇人費の現物支給など)→現物を金額に換算して、収入・経費に同じ額を計上
雑収入:
・農作物に対する各種共済金・補償金
・農作業の受託収入(田植え・刈り取り・乾燥調整など)
・農業の各種補助金・奨励金(国などからの給付金など)
・営農組合からの役員報酬・出役賃金・機械賃借料など
▽必要経費
雇人費:農作業の労賃や現物支給、請負耕作料、賄費など
小作料・賃借料:小作料(農地などの賃借料)、農機具の賃借料、共同施設使用料(ライスセンターやカントリーエレベーター)
減価償却費:取得価額10万円以上の農業用建物、機械・車両などの償却費
貸倒金:売掛金などの貸倒損失
利子割引料:農業用資産を取得するための借入金の支払利息など(ただし、元金部分は必要経費になりません)
租税公課:農業部分の固定資産税、自動車税(取得税・重量税含む)、不動産取得税、水利費などの公課
種苗費:種子・苗・種いもなどの購入費用
素畜費:子牛・子豚・ヒナなどの取得費、種付け料
肥料費:肥料の購入費用
飼料費:飼料の購入費用