- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県登米市
- 広報紙名 : 広報とめ 2月号(357号)
■豊かさを求めて新しい農福連携の形へ
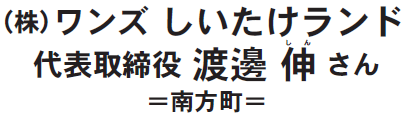
◇農業と障がい者支援で創造する企業
就労継続支援A型事業所「しいたけランド」は、2010年創業。「福祉と農業の融合」をコンセプトに、障害者雇用事業を展開しています。設立当初は10人ほどでシイタケを栽培していましたが、雇用人数の増加に伴い、年間を通して作業できる方法を模索し、ネギ栽培を開始しました。
現在、経営規模はシイタケ約1万7千菌床、長ネギ畑約240アール。従業員は利用者とスタッフ合わせて36人で経営しています。
◇働く人の地震や生きがいを生み出す
障がいの内容や程度は人によってさまざま。「いろいろな人が、得意な分野や強みを生かせるようなアシストをするのが私たちの役割です」と話す、渡邊伸さん。
シイタケ生産部門を担当する千葉健太(けんた)さん(登米町)は勤続10年。以前は理容店を経営していましたが、病気の後遺症で手にまひが残り、現在の仕事に転職しました。「幅広い年代の人たちと一緒に働けるのは常に新鮮です。ここで作ったシイタケの味は最高なので、ぜひ食べてみてください」と笑顔で話す千葉さん。
佐々木義幸(よしゆき)さん(石越町)は、ハウスや畑の管理、防除などを担当。「自分のペースで、知識や経験を生かした仕事ができる。風通しの良い職場環境に感謝しています」と話す佐々木さんは、スマート農業普及推進事業で導入した農業用ドローンの操縦もこなします。「ドローン作業はとにかく時短できる。また、畑がぬかるんでいても対応でき、作業効率は格段にアップしました」と効果を実感しています。
◇社会の変化やニーズを捉え、まい進を続ける
同社は昨年10月、県内初の「ノウフクJAS(※)」を取得。今後も、会社としての能力や事業規模などを見極めながら、新たな取り組みの導入を検討したいとする渡邊代表。「人や地域が『豊かさ』を感じられることを長く続けていきたい」と歩みを進めています。
※障がい者が生産工程に携わった食品などの日本農林規格
■スマート農業の普及促進に向けて
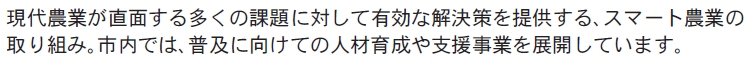
![]()
登米総合産業高校は、企業やみやぎ登米農業協同組合の協力を得て、スマート農業に関する連携授業を実施しています。
本年度は、農業科の生徒が最先端の自動操舵田植機を使用した実習を受講したほか、ドローンを使った農薬・肥料散布、水位センサー導入、稲刈りなど、年間を通してスマート農業を実践。若い世代の人材育成につなげています。
問合せ:登米総合産業高校(農業科)
【電話】0220-34-4666
![]()
農業における担い手の減少や生産現場での人手不足が深刻化する中、生産性の効率化や省力化が求められています。そこで、本市では、ICT、IoT(※)などの最先端技術を活用したスマート農業機械などの導入を支援するため、令和2年度からスマート農業等普及推進事業を実施しています。これまで、多くの生産者にこの事業を活用していただき、推進に努めてきました。
さらなるスマート農業普及のため、令和6年4月には、具体的な施策や営農体系モデルごとの取り組みなどを盛り込んだ「登米市スマート農業推進方針」を策定しました。今後は、方針で掲げた「省力化・効率化による持続的な農業」「誰もが取り組める農業」「環境に優しい農業」を実現するため、国・県などで実施している機器導入支援情報の提供や新規就農者などに対する、最新の技術内容や機器を紹介するセミナーを開催します。
※ICT、IoT…インターネットを介して、人やモノ同士のコミュニケーションを可能にする技術
![]()
問合せ:産業経済部農政課(農産園芸係)
【電話】0220-34-2713
