くらし 議会だより
- 1/17
- 次の記事
- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県西ノ島町
- 広報紙名 : 広報にしのしま 令和7年3月号
■第516回西ノ島町議会12月定例会一般質問(要約)
◆小島 正春 議員
◇「ふるさと館」食堂部分の再開について
観光客の方から、食事をする場所が無いといった声を今年は特に耳にするようになった。せっかく来島し本町を楽しんでも、食事をする場所が無いと、西ノ島に来た喜びが半減してしまうのではないか。
町の所管である「ふるさと館」食堂部分は今年一年閉店したままとなっている。
西ノ島町の玄関口である別府港周辺のにぎわい創出、ひいては本町の活性化のために「ふるさと館」食堂部分の再開は急務であり、今後の営業再開に向けた町長の所信を伺う。
回答:町長
「ふるさと館」の食堂部分は、今年(令和6年)1月から休業状態である。
町としてもこの状況を看過していた訳ではなく、事業者と再開に向けて協議を重ねてきた。また、事業者側でも営業再開の道を探ってこられた。しかしながら休業が長期に及び、その直接の理由であるスタッフの確保に目処が立たないということで、11月に最終協議を行い、残念ではあるが現事業者による営業の継続を断念することとして、後継事業者の公募に向けた準備に着手したところである。
今後は、新たな事業者が決まれば、関係機関との調整を行い、早期に食堂が再開できるように取り組んでいく。
◆仲吉 正 議員
◇島前大橋架橋事業について
県道319号線(西ノ島・海士線)は、島前大橋架橋事業の採択に伴い、西ノ島と中の島を架け橋で結ぶ目的で昭和55年に一般県道として認定されたが、平成15年に県の公共事業再評価委員会に諮られ、事業休止となって、現在までその状態が続いている。
人口減少が顕著である両町を架橋で繋ぐことで、生活圏を一体化することによる様々な効果があると考えられる。
将来のまちづくりの基盤となるであろう島前大橋架橋事業について、町長の所信を伺う。
回答:町長
平成10年代に国の三位一体改革により地方の財政状況が悪化した中で、島前大橋架橋という大事業は隠岐管内における他の公共土木事業に与える影響が大きいこと、事業を継続した場合の費用対効果が非常に下がっていること、また一方では内航船やフェリーの充実、両島における人口の減少など社会情勢の変化もあり、県において事業休止という判断がなされたと認識している。
20年以上前に下された休止という県の判断、その後も財政状況は厳しい状況が続いており、これが劇的に変わることは今後もないであろうと考えている。
島前町村組合が運営する内航船事業が、住民生活に密着した交通手段となっており、島前地域の持続的発展のために、町村組合を構成する海士町や知夫村とも連携しながら、引き続き安全、安心かつ利便性の高い航路として維持していくことが使命であり、また現時点での最善策と考えている。
◆柴田 輝 議員
◇自動運転バス導入に向けた実証実験の実施について
本町では町営バスの運行本数が限られており、特に高齢者の方々が買い物や通院の際の交通手段に不安を感じている。
運転免許の返納を躊躇する方、車を持たないことで本町への移住を諦める方々もおり、人口減少や地域活性化への影響も懸念される。
この課題を解決するため、自動運転バスの導入に向けた実証実験の実施を提案する。これにより、将来的には住民の移動手段の確保と交通の利便性向上が期待できると考えるが、町長の所信を伺う。
回答:町長
本町の路線バスは、幹線部分で1日に10~11便を運行しており、通勤や通学、通院など日常生活でのご利用や、観光やビジネスでの来島者の2次交通としてもご利用をいただいている。幹線以外の路線については1日3便の運行、それとは別に買い物支援バスを運行して、住民の皆様にご利用いただいているところで、人口規模など類似した近隣の自治体と比較すれば充実した路線バス運行体制を維持できていると考えている。
路線バスに代表される地域公共交通、生活交通という部分は、様々な形で住民の暮らしに関わるため、こうした路線や便数を維持していくことが重要であるとの認識を持っている。
自動運転バスの実証実験については、本町の実情に照らし、どういった形が現実的な選択肢となり得るか、といった方向性について検討していきたい。
◆町議会12月定例会の概要
◇12月12日(木)
本会議 ※傍聴者11名
・町長諸般の報告並びに提出理由説明
・議長諸般の報告
・一般質問(3名)
・議案説明(議案12案件)
◇12月13日(金)
常任委員会による審査
本会議
・常任委員会審査報告
・質疑・討論・表決(議案12案件全て原案のとおり可決)
・西ノ島町選挙管理委員及び同補充員の選挙(委員4名、補充員4名の当選人を決定)
・閉会中の継続調査等の申出(了承)
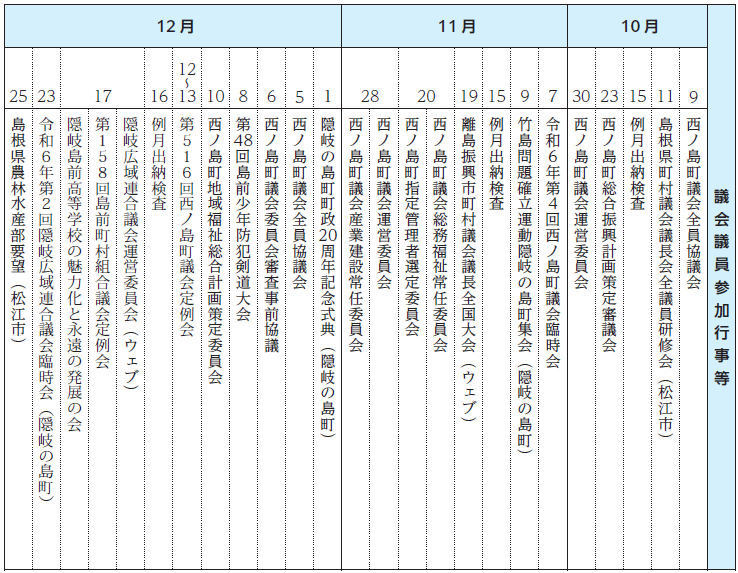
西ノ島町議会 広報調査特別委員会
