- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道ニセコ町
- 広報紙名 : 広報ニセコ 令和6年11月号

◆みんなで学び、考え、たくさんのアイデアが生まれました
令和5年度までに、延べ262人の児童・生徒が小・中学生まちづくり委員会に参加してきました。そして、令和6年度小・中学生まちづくり委員会の委員は、21人。6月28日のオリエンテーションから始まり、これまで4回の活動をしてきました。活動の中で、子どもたちは何を見て、考えたのでしょうか。
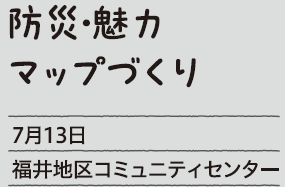
町と福井地区親交会、小・中学生まちづくり委員会、福井地区代表小・中学生、北海学園大学、HBCとの協業プロジェクトとして行われた「福井地区防災・魅力マップづくり」。
はじめに、福井地区親交会の矢島さんから福井地区の歴史や取り組みについて学びました。その後、「福井地区班」と「相馬地区班」に分かれてフィールドワークを行いました。歴史のある場所や景色がきれいな場所のほか、浸水想定区域がどこか確認しました。最後は、福井地区と相馬地区の防災マップと魅力マップを作成し、発見したことや地域の魅力を発表しました。
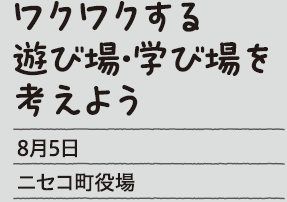
マインクラフトで未来のニセコを作るワークショップに向けて行われた「ワクワクする遊び場・学び場を考える」アイデア共有と意見交流。
はじめに、ニセコ町の「お気に入りポイント」、「変わってほしいところ」、「未来はどうなっているか」の3カテゴリーについて、5グループに分かれてアイデアを共有し、ワクワクする遊び場・学び場を考えました。そして、模造紙に意見をまとめ、グループごとに発表しました。
その後、マインクラフトを使ったまちづくりの研究などに取り組んでいる慶応義塾大学の三國さんから、現代の最新テクノロジーや、町外の遊び場などを紹介していただきました。
最後は、現役地域おこし協力隊で株式会社ニセコ雪森考舎にも携わっている清部さんから、森林保全や自然の循環について話を聞いた後、木のスプーンづくりに挑戦。ニセコ町の木材で作られた木のスプーンキットを使い、型からスプーンを取り出して紙やすりで磨きました。目の粗さの異なる3種類の紙やすりを使い分け、角ばった部分を丸くしたり、持ちやすい形に変えてみたり…。一人ひとりのオリジナリティを発揮し、世界に一つだけのマイスプーンを完成させました。
◇マインクラフトとは…
電子版ブロックゲームのこと。建築物を作ったり、アイテムを組み合わせてものづくりをしたり、自分だけの仮想空間を作ることができます。
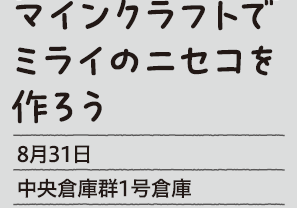
町と慶応義塾大学システムデザインマネジメント研究科山形研究室との協業プロジェクトとして行われた「マインクラフトで未来の遊び場・学び場を作ってみようワークショップ」。
はじめに、最新のテクノロジーを体験。生成AIによる画像生成技術やARを実際に体験しました。最新技術でできる数々の体験に、子どもたちのワクワク感が高まっていきます。
その後、4つのグループに分かれてニセコ町の未来の遊び場・学び場を考えていきます。「こんな遊び場があったらいいな」や、「こんなことができたらいいな」、「これは変えたいな」など意見を出し合います。遊び場・学び場にあるものと未来にできたらいいことのアイデアを掛け合わせ、実際にマインクラフトでミライのニセコを作りました。そして、自分たちが考えて作ったものを伝え、アイデアを共有することも大事なこと。どうしてこれを作ったのか、自分がどう思ったのかを説明しました。
子どもたちが考えるアイデアには、子どもならではの目線でたくさんの工夫が考えられていました。ミライのニセコを考えることで、今のニセコ町について改めて考えるきっかけになったのではないでしょうか。
