- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都杉並区
- 広報紙名 : 広報すぎなみ 令和7年9月15日号 No.2412号
■デフリンピックとは
「耳がきこえない・きこえにくいアスリートのための国際スポーツ大会」のことで、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)の主催で4年ごとに開催されます。参加資格は、補聴器などを外した状態で普通の会話程度の音(55dB以下)がきこえないことです。競技中は補聴器などの使用が禁止され、国際手話・スタートランプ・旗など、視覚情報を活用したコミュニケーションが特徴です。
■デフビーチバレーボール
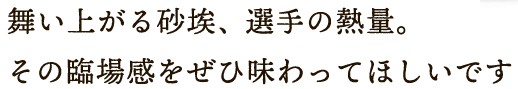
東京2025デフリンピック日本代表
デフビーチバレーボール選手
伊藤碧紀
プロフィール:伊藤碧紀(いとう・たまき)
平成16年杉並区生まれ。都立中央ろう学校卒業。大東文化大学在学中。中学生のときにバレーボール部に入部し、その後ビーチバレーボールも始める。高校時代の同級生・堀花梨選手とペアを組み、全日本デフビーチバレーボール選手権2023年、2024年大会ともに優勝。東京2025デフリンピックでもメダル獲得を目指す。
─ビーチバレーボールを始めたきっかけを教えてください。
もともと中学校の部活でバレーボールをやっていて、部活を引退した中学3年生の冬に母に連れられてビーチバレーのクラブに体験に行ったのがビーチバレーとの出会い。「こんなスポーツがあるんだ」と初めて知りました。私は先天性の難聴で、程度は比較的軽め。女性の声は聞き取りやすく、コーチが女性だったこともあり、特に音で困ることはなくプレーできました。足の強さには自信があり、動きにくい砂の上でも走るのは余裕だったけれど、ジャンプするのは大変で…! 練習を重ねるうちにビーチバレーの魅力にはまっていきました。
─高校ではバレーとビーチバレーを両立されていたそうですね。
高校でもバレー部に入部し、同時にビーチバレーのクラブも継続して、高校3年間はとにかくバレー漬けの毎日でしたね。バレーで身に付く基本の技術はビーチバレーにも応用できますが、ビーチバレーで求められる特徴的な技術もたくさんあるので、それらを習得して磨いていく必要がある。大学進学以降はビーチバレーに絞って取り組むことにしました。
─ペアを組む堀花梨選手は高校時代の同級生だとか。
彼女も同じバレー部でした。私から「ビーチバレーを一緒にやってみない?」と誘ったら、「うん、オッケー」という感じで即決してくれて(笑)。それから二人で練習を重ねていきました。目指せる大会は全て目指そう、世界選手権やデフリンピックなどに全部出よう!と花梨と話してきたので、今回のデフリンピック出場は一つの目標がやっと叶ったという感覚です。全力でメダルを取りに行こうと思います。
─デフビーチバレーはどのような競技ですか?
笛の代わりにネットを揺らすことで判定を伝えるといったこと以外は、ビーチバレーと同じです。コミュニケーションは基本的に手話。プレー中にボールが動いているときは手話ができないので、大きな声で叫ぶこともあります。私は補聴器を外していても、「上!」など大きな声で言われればある程度聞こえます。一方、聞き取るのが難しい花梨に対しては、大きな身振りで「あっち!」とか、そんなふうにコミュニケーションを取ることも多いです。
─競技のどんなところに注目して見てほしいですか?
ポイントは二つあって、まず一つは、動きにくい砂浜で選手が素早く移動する動きと、その力強さ。砂浜でのジャンプはすごく筋肉が必要なので、選手の筋肉美もぜひ見てほしいです。もう一つは、選手の頭の使い方。相手がどう動くのか、風の向きでボールがどう飛ぶのかなど、全てを頭の中で読みながら計算して得点を狙っているので、戦略にも注目してみてください。ビーチバレーはコートと観客席がとても近いので、選手の表情までよく見えるのがいいところ。自分ならこっちに動くかな?とか、距離が近いからこそ想像しながら観戦すると、とても楽しめると思います。
─最後に、区民の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
ビーチバレーはすごく運動量の多い競技で、プレイヤーが2人しかいない中でラリーを交わして戦わなければなりません。その必死さだったり、舞い上がる砂埃だったりを間近で感じていただけたら、きっと感動してもらえるのではないかと思います。ぜひ会場に来て、私たちの熱量を感じてほしいです!
