- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県紀宝町
- 広報紙名 : 広報きほう 令和7年9月号
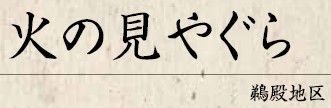
今回は、鵜殿地区にあった火災の早期発見と警報を目的に設けられた「火の見やぐら」をご紹介します。
火の見やぐらは、江戸時代から昭和初期にかけて全国ほぼすべての地域に整備されましたが、自治体による消防団の包括、電話の普及と119番による通報体制の整備、サイレンや防災行政無線などの整備により、現在はその役目を終え、ほとんどの火の見やぐらは撤去されました。
町内には現在、火の見やぐらは残っていませんが、昭和27年から28年ごろに撮影された火の見やぐらの写真が残っており、現在の町役場裏あたりに存在していた立派なやぐらの姿が確認できます。
火の見やぐらはひとつとして同じ形状はないといわれており、鵜殿のものは三本の筋交入りの足に三角の見張り台、四角形屋根の下に半鐘が吊るされたデザインで、石造りの基礎も見られます。
かつて鵜殿のまちを見守っていた火の見やぐらは、今はその姿こそありませんが、当時の暮らしや地域の防災の歴史を今に伝えてくれています。写真に残るその凛とした姿から、地域を支えた人々の思いを感じることができます。
