- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県日田市
- 広報紙名 : 広報ひた 令和7年7月号
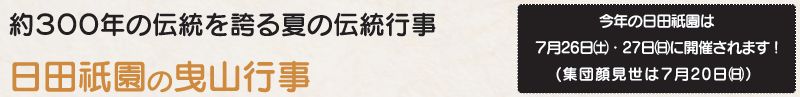
祗園社の祭神は、牛頭天王(こずてんのう)(素戔嗚尊(すさのおのみこと))と言い、悪疫鎮護の荒神様です。市内には、隈・豆田や池辺・蕪などに400~500年以上前から祗園社があり、それぞれ祭礼が行われてきました。正徳4(1714)年ごろに隈・豆田で山鉾が作られるようになり、祭が盛んになりました。
その後、山鉾の製作技術の発達や道路の整備によって、山鉾は次第に高くなり、文化・文政期(1800~1820年代)には12~15mにも達しました。隈も豆田も山鉾作りに腕を競い、緋羅紗地(ひらしゃじ)に金糸銀糸を用いて虎や鳳凰などが刺繍された見送幕や水引幕なども作られ、豪華さを競うようになりました。
「日田祇園の曳山行事」は、平成8年に国の重要無形民俗文化財の指定を受け、平成28年には「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。
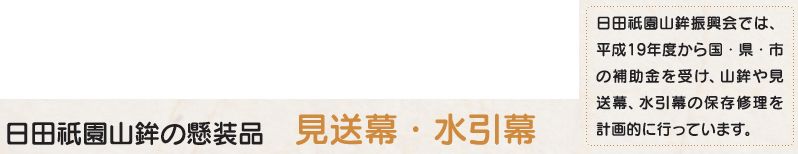
国の重要無形民俗文化財に指定されている日田祗園山鉾の懸装品は、江戸時代後期から明治期にかけての幕が数多く伝来しており、その歴史的、美術的価値は高い。見送幕・水引幕など、山鉾を飾る幕類は、日田の祗園祭を彩ってきた。
江戸時代の幕類は、京都または長崎などで刺繍されていた。長崎刺繍は長崎くんちの幕の刺繍として、いまなおその技術が伝承されている。長崎刺繍が長崎以外で、まとまって残されているのは日田だけだと思われる。日田と長崎は幕府の代官所のあった所で、政治・文化・経済関係も深く、それが長崎刺繍による見送幕や水引幕が日田に残されている要因と考えられる。明治時代になると大阪でも製作されるようになった。
また、見送幕と水引幕の下絵を、大阪の絵師・森祖仙や長崎の木下逸雲、地元隈町の亀州が描いていることが判明している。
これら日田祗園山鉾の懸装品は貴重な歴史・美術資料であるが、修理の際に詰め物を増量して原型を損ねているものも多い。また、刺繍の綴じ糸が切れているものもあり、将来、製作当初の姿に復元修理をする必要性がある。日田の文化水準の高さを広く知ってもらい、地域の誇りうる文化遺産であることを示すことのできる資料群である。そのために日田の文化を伝える日田祗園山鉾懸装品の保存の措置を講じる必要性は高い。
日田市文化財保護審議会会長別府大学名誉教授 段上達雄
日田祇園は古くから疫病退散の願いを込めて神事を行い、巡行してきました。その山鉾に懸けられる見送幕や水引幕は各町が日銭を貯め、京都や大阪、長崎で製作したものです。古いものでは、江戸時代に製作されており大変貴重なものが残っています。
日田祇園山鉾振興会長 草野圭次
