- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県横須賀市
- 広報紙名 : 広報よこすか 令和7年9月号
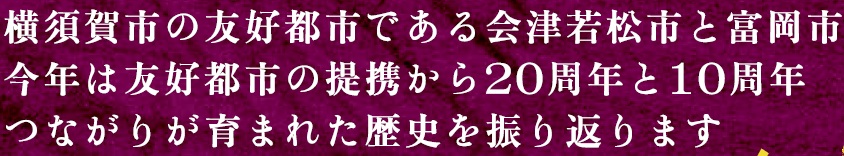
■〔三浦一族の縁が育む〕横須賀市×会津若松市
会津若松市とのつながりは、鎌倉時代に源頼朝と共に活躍した三浦一族が、戦の功績により会津の地を与えられたとされることに始まります。
その後、江戸時代には会津藩が三浦半島沿岸の警備を担当。多くの藩士が横須賀で暮らしました。深い歴史的な関わりを背景に友好都市として、今もなお、より深い絆を育んでいます。
◇家紋・横須賀市市章(本紙をご覧ください)
三浦一族の家紋。本市の市章の中央部も、市名の頭文字「ヨコ」を「丸に三つ引」風にデザインしている。
◇全国に広がった名族「三浦一族」とは
平安時代の終わりごろ、相模国(さがみのくに)〔現在の神奈川県の大部分〕の三浦郡を領地とし、「三浦」を名乗った武家。衣笠城を拠点に三浦半島一帯を統治し、源氏と結びつきを深め、勢力を広げていきました。
三浦一族は、鎌倉幕府創設に尽力し、後には戦国大名としても活躍した名族といえます。市内には、ゆかりの寺社や仏像などが多く残されています。
◇会津藩士をしのぶ市民団体
市民主体の「三浦半島会津藩士顕彰会」は、年次法要や墓所の維持管理、歴史ツアーを実施。
江戸湾防備を務めた会津藩士たちの思いを引き継ぐため、今もなお、顕彰を続けています。
■〔世界遺産がつなぐ〕横須賀市×富岡市
横須賀製鉄所と富岡製糸場は、日本の近代化を象徴する二つの拠点。横須賀で培われた西洋式の建築技術は、富岡製糸場の建設に生かされました。横須賀製鉄所の木骨レンガの工法が、富岡でも使用されています。技術や資材の交流が両市を結び、横須賀製鉄所(造船所)創設150周年を機に、友好都市に。現在も相互交流を深めています。
◇時代を超えてつながる交流の証
2012年に富岡製糸場の敷地から横須賀製鉄所(造船所)のレンガが出土。横須賀製鉄所と富岡製糸場の間に技術や資材の交流があったことを裏付ける出来事として、注目を浴びました。
◇横須賀に残る、近代化の歴史
ヴェルニー公園内にあるティボディエ邸では、富岡製糸場と同じトラス工法の小屋組みを当時の邸宅の部材で移設再現。館内には、横須賀製鉄所のレンガの実物も展示しています。
■鎌倉→室町→安土桃山→江戸→明治→・・→平成→令和
◇〔鎌倉〕三浦一族の活躍から生まれたつながり
奥州合戦(1189年)では、源頼朝が東北地方を支配していた奥州藤原氏を滅ぼしました。
これにより、鎌倉幕府は東国支配を強化。
三浦一族はこの戦いに頼朝方の有力な武士団として参戦しました。佐原義連(さはらよしつら)〔三浦大介(おおすけ)義明の子〕は、その活躍により、頼朝から会津(現在の福島県西部)を与えられたと伝えられています。会津とのつながりは義連から生まれたとされ、現代にも語り継がれています。
◇〔室町〕会津若松城は三浦一族に由来あり
奥州合戦に貢献した義連の子孫は、芦名氏(※)を名乗り、会津に移住。14世紀半ばには、芦名直盛が活躍し「黒川城」を居城としたとされます。
この城は、現在の会津若松城(鶴ヶ城)の前身であり、会津と横須賀の深い縁が感じられます。芦名氏は16世紀中頃に最盛期を迎え、東北地方有数の戦国大名として、摺上原(すりあげはら)の戦いで伊達政宗に敗れるまで、会津に君臨しました。
※…時期により、「葦名」または「蘆名」とも表記
◇〔江戸〕三浦半島を守った会津藩士たち
19世紀初め、日本近海に外国船が現れたことを受け、幕府は江戸湾の沿岸防備を全国の大名に分担させていました。その一部を任された会津藩は、三浦半島の要所を守ることに。鴨居や三崎を拠点に、観音崎や浦賀の平根山などに台場を築き、武家の学校である藩校も設立。家族と共に横須賀へ移住し、生涯を終えた会津藩士も多く、今でも市内には藩士とその家族の墓所が残されています。
◇〔明治〕世界遺産のルーツは横須賀製鉄所
富岡製糸場の設計に関わったフランス人のバスチャンは、横須賀製鉄所の建築技師で、近代的な工場建築などの設計担当者でした。また、木造の骨組みにレンガを積み上げる工法や、従来の日本にはなかった屋根の工法(トラス工法)は、横須賀製鉄所がモデル。富岡製糸場のルーツが横須賀製鉄所にあったことがうかがえます。
■未来へつなぐ、交流の輪
歴史的な関わりを背景に、友好都市として、まちや市民同士の絆を深めています。さまざまな交流を重ね、お互いのまちの魅力や伝統への理解が広がってきました。これからも、文化・スポーツなどの市民活動、観光などの産業、さらには災害時の支え合いなど、幅広い分野で連携し、豊かな暮らしや地域の発展につなげていきます。このつながりを一緒に育てていきましょう。
問合せ:国際交流・基地政策課
【電話】822-8138
