- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長崎市
- 広報紙名 : 広報ながさき 令和7年3月号 No.890
■今も変わらず大切にしている学び
ICT機器などの導入で教育のデジタル化が進んでも、これまでと変わらず大切にしている学びがあります。それは、対話や対面での交流を重視した授業や、体験学習からしか得ることができない深い学びです。また、長崎の歴史や特徴を生かした長崎ならではの学びも大切に、誰一人取り残すことなく子どもたちがのびのびと育つ教育環境をつくり続けています。
◆対話型平和教育の実践
平和について考え、話し合い、発表を重ねていく中で主体的に学びを深めていく学習です。他人の意見に耳を傾け、自分の言葉で平和の大切さを発信できる力を身に付けてほしいという思いを込めて、この学習を実施しています。
◆ハローイングリッシュ活動
市独自の取り組みとして、外国語の授業が始まる前の小学1・2年生が英語に触れるきっかけをつくっています。国際色豊かな長崎で育つ子どもたちに国際感覚を養ってほしいという思いで、ALT(外国語指導助手)を他都市より多く採用するなど、英語教育にも力を入れています。
◆ながさきの魅力発見・発信学習
進化を続ける長崎の歴史や伝統、特産品などに関する学習や体験を通して学んだ新たな気付きや発見を発信しながら楽しく学びを進めています。ふるさと長崎に誇りを持ち、未来の長崎を子どもたちの力で切り拓いてほしいという思いを込めて、幅広く教えています。
◆書くことも大切な学び!
ICT機器などのデジタルと、ノートや黒板などのアナログのそれぞれの良さをバランス良く活用して学習を進めています。
◆「あ・は・は運動」実施中!
「あ」いさつ・返事、元気よく!
「は」や寝・早起き・朝ごはん!
「は」き物そろえ、いい気持ち!
普段の生活の中でもいろんな力を身に付け、健やかに育ってほしいという思いで、学校と家庭と地域が連携し、この運動に取り組んでいます。
◆誰一人取り残さない学びの支援
市では、不登校やその傾向にある子どもたち一人ひとりのニーズに合わせた、多様な学びの場や機会を提供しています。心配なことがあれば、まずはご相談ください。
▽在宅での学習支援
自宅から出ることができなくても、学び続けることができるようICT機器を活用しながら、デジタル教材やテレビ会議システムなどを使った学びの支援をしています。4月からは新たに、インターネット上の仮想空間(メタバース)の中で、交流や面談、学習ができる「メタバース登校システム」も開始します。
▽学びの多様化学校
特別な教育課程を編成した県内初の学びの場で、桜馬場中学校の分教室として来年4月から市民会館内に開校します。文部科学省が定める学習指導要領の基準によらず、授業時間数や学習内容を設定できるため、不登校生徒の事情に配慮した柔軟な対応ができます。また、一般の学校と同じように卒業資格を得ることができるのもポイントの一つです。
▽学びの支援センター
市民会館に開設している「ひかり」では、個別での学習指導や小さな集団での体験学習や遊びなどを通して、子どもたちが社会的自立に向けた力を蓄えています。また、登校はできても教室に入ることができない子どもたちのために、必要とする全ての小中学校内に「校内学びの支援センター」を開設しています。専門の支援員を配置し、教職員や他の児童・生徒との交流をサポートしています。
・保護者の声
周囲の目を気にせず、自分らしく過ごす時間が増えてきたようです。また、先生との距離も近く、似た境遇の友達もいるため、安心してさまざまな活動に取り組んでいます。それが、達成感となり、少しずつ自信につながっているようです。
▽保護者のサポート
不登校児童・生徒の保護者が集まり、情報交換を行ったり、不安や悩みを共有したりすることができる「保護者座談会」を毎月1回開催しています。会には、臨床心理士をコーディネーターとして招き、保護者の不安を少しでも和らげるサポートを行っています。
問い合わせ:教育研究所
【電話】824-4814
■子どもたちの健やかな成長を願って
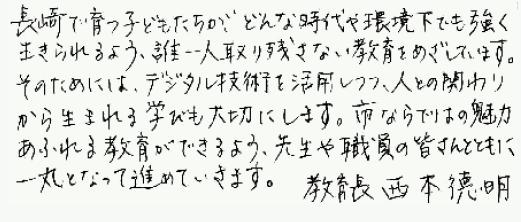
問合せ:教育委員会総務課
【電話】829-1191
