文化 戦後80年 未来へつなぐ記憶(1)
- 1/46
- 次の記事
- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県大村市
- 広報紙名 : 広報おおむら 2025年8月号(No.1552)
先の大戦終結から、今年で80年を迎えます。
今だからこそ、平和について考えてみませんか。
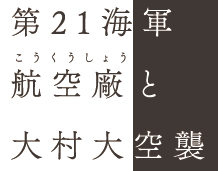
明治以降、陸軍歩兵第46連隊や大村海軍航空隊の設置など、大村は軍都としての歩みを進めていました。
太平洋戦争が始まる直前の昭和16年10月、現在の古賀島地区に設置されたのが、第21海軍航空廠です。ここは、主に零式水上観測機などの航空機とエンジンの製作・修理を行う軍需工場で、多くの軍人や工員のほか、学徒や女子挺身隊といった子どもや女性、台湾や朝鮮などの人々も動員されました。
戦況が悪化すると、工場を拡張。昭和19年には放虎原をはじめ市内各地に施設を有し、工員・学徒など約5万人※を要する東洋最大級の航空廠とも言われていました。
太平洋戦争中、国内の多くの都市や工場が空襲を受ける中、大村も軍の施設が多数あったことから、敵の航空機による偵察が行われたり、何度も爆弾が落とされたりするなど、攻撃の標的となりました。
そして、昭和19年10月25日の朝。航空廠の上空を多数の爆撃機B29が何度も飛来し、624発もの焼夷弾や爆弾を次々と投下。1時間もの間、攻撃を受け続け、およそ250人の死傷者を出しました。
※航空廠の面積や人数に関する公的機関による資料は残っておらず、諸説あります。
(参考文献:新編大村市史第四巻/放虎原は語る/第二十一海軍航空廠沿革史)
◆戦争だけは、絶対に駄目
◇戦争体験者 笹山 トヨ子さん(100歳)
戦時中、海軍施設部に勤めていた笹山さんは、海軍関係の施設建設に携わっていました。「あの頃の空襲は夜中でも何でもおかまいなし。低空飛行する敵機が見えたと思ったら、突然ババババッと、こちらへ向かって撃ってきた。そのようなことが複数回ありました」
大空襲のときは航空廠から離れた場所にいて無事でしたが、敵機が数機ごとに飛来し、何度も航空廠を波状攻撃していた、と当時の様子を語ります。「大空襲後も空襲は続きました。空襲後の航空廠は破裂した爆弾でやられて血まみれの人、亡くなっている人もいたし、何十人も入っていた防空壕は全滅。今の人たちは、きっと耐えられないと思います。あんなむごい話、聞かせたくない。戦争だけは絶対にしたら駄目。戦争は惨め。平和な日本でいてほしいですね」
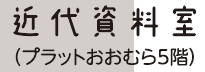
第21海軍航空廠関係の資料を中心に、廃藩置県後から終戦後までの大村の歴史を紹介しています。
時間:10:00~18:00
料金:無料
休館日:月曜・年末年始
近代資料室に関する問合せ:歴史資料館
【電話】48・5050
![]()
市内には大村海軍航空隊や第21海軍航空廠があった古賀島地区を中心に、数多くの戦時中の遺構が残っています。
・皆同砲台跡|皆同町
福重出張所裏にある今富城跡の高台に築かれた砲台。高射砲の砲座などの遺構が残っています。
・慰霊塔公園|松並2丁目
防空壕の上には、航空廠での空襲による殉職者を祭るための慰霊塔が建てられています。
・掩体壕(えんたいごう)|原口町
下原口公園内に残っている、大村海軍航空隊が設置した航空機用の防空施設です。
・第21海軍航空廠本部防空壕跡|古賀島町
航空廠本部庁舎前に設置された防空壕の遺構。無数に残る弾痕は、空襲の恐ろしさを物語っています。
・楠のある通り|松並交差点~県道38号長崎空港線間
市民病院前の通りは、かつて航空廠の正門からの道筋でした。現在も道路として利用されています。
※詳細は本紙をご覧ください。
