くらし 認知症とともに生きる 自分らしさ、その人らしさを守る(1)
- 1/31
- 次の記事
- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県矢巾町
- 広報紙名 : 広報やはば 令和7年9月号
認知症――。あなたはどんなイメージを持っていますか?
国が令和6年12月に示した認知症施策推進基本計画で新しい認知症観が示されました。「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる」という考え方です。
ここでは、認知症になっても好きなことに取り組み、自分らしく生きる町内の方の紹介に加え、岩手医科大学の専門医からのアドバイスも掲載しますので、「認知症」に対する向き合い方を考えてみましょう。
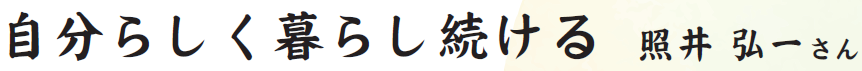
認知症は「できないこと」ではなく、「その人らしさ」を支え合いながら共に生きる新しいステージです。本人の意思や好みを尊重し、地域や家族と手を取り合い暮らし続ける――。そんな共生社会の一員として、模型づくりを趣味に前向きに生きる照井弘一(こういち)さんは、今日も自分らしい日常を紡いでいます。
![]()
「自分自身が楽しめることをやれていれば、症状の進みを遅らせることができる」と話す照井さん。模型作りは長年の趣味で、ジオラマも見事に仕上げる腕前(写真左上)。幼少期に徳田にあった商店で模型の世界と出会い、社会人になってからは離れていましたが、50歳ごろに医師の勧めで再開しました。
30代から40代にかけて、仕事で多忙だった中でうつに。その後、アルツハイマー型認知症を発症しました。治療の中で、同じく模型好きの医師と出会い、完成した作品を見せ合うように。模型に加え詩も書くなど(右上「らぶれたー」)、創作活動に意欲をみせています。町役場の敷地内にある「町えんじょいセンター」では、模型の個展も開催。来場者から好評を博しています。
「以前と比べると、手を付けて集中するまでの時間が掛かるが、一度集中してしまうと、呼ばれても気が付かないようです」。夢中になって取り組める趣味は、照井さんが自分らしく生きるための原動力です。
※詳しくは本紙をご覧ください。
![]()
町えんじょいセンターで毎月第2土曜日に行われる「おれんじカフェ」は、認知症の方やその家族、介護などに悩む方など、どんな方でも参加できる場です。認知症に関する研修を受けたスタッフと会話する時間は照井さんにとってかけがえのないものになっています。
「近況を話すし、スタッフの方もいろんな話題を出してくれる。会話のキャッチボールが楽しい。誘われたときは参加しようか迷ったが、今では月1回の楽しみです」と照井さんは話します。
![]()
「主治医は『(自分が認知症と)認めることが大事』ということや『他の人に堂々と話して、ちゃんと伝えておいた方が、相手も理解してくれる』という話をしてくれた」。早期から適切なかかりつけ医を持ち、症状や今後の生活へ助言をしてくれる存在が、照井さんの生活の助けになっています。
「認知症とともに生きること」に対して当事者も、その周囲の人も正しく知り、理解しようとする姿勢が必要です。
照井さんは「認知症は年齢に関係なく、若い方も発症しうる病気。好きなこと、自分にとっては模型を作ることですが、それを続けることで、認知症の進行を遅らせることができていると思います。また、困っている人を見かけたら、間違いを恐れずに声を掛けてほしいです」と話しました。
