- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府長岡京市
- 広報紙名 : 広報長岡京 2025年8月号
■2.もしものために、今できる「準備」を
●マイ・タイムラインを作る
大雨や台風による災害が起こったとき、「いつ・どこに・どのように避難するか」をあらかじめ決めておくことが重要です。自分の行動を時系列で整理する「マイ・タイムライン」を、台風シーズンの前に作成しておきましょう。
「いざという時は、慌てず計画通りに行動を!」
○準備するもの
・ハザードマップ
・マイ・タイムラインの台紙
・筆記用具
台紙や作成方法は市HPにも掲載中
(1)避難する場所は?
例)自宅の2階、●●小学校
(2)避難に必要な準備は?
例)常備薬の確認
子どものミルク・おむつの準備
(3)避難開始のタイミングは?
例)「高齢者等避難」で祖父が自宅の2階へ避難
(4)[プラスワン]地域住民としてできることは?
例)近所へ避難を呼びかける
(1)~(4)の順に考えてみよう!
○ここがポイント!
避難所に行くだけが避難ではありません。浸水の深さを確認した上で、自宅の上階に避難する「垂直避難」も有効です。
※詳細は本紙をご覧ください。
●避難時の持ち出し品をまとめる
スムーズに避難できるように、持ち出すものをかばんにまとめておきましょう。無理せず運べる重さにするのがポイントです。持ち出し品の例は、ハザードマップにも掲載しています。
○準備しよう!持ち出し品
・貴重品(通帳・免許証のコピーなど)
・衣類・タオル
・常備薬
・非常食・水
・懐中電灯
・ラジオ
・おむつ など
自分たちの生活に必要なものを準備しておきましょう!
●空き家や竹やぶなどの安全確認
○空き家を所有している人は…
屋根瓦やシートなど、落下しそうなもの・飛びそうなものがないかを確認しておきましょう。相談は、空き家のある自治体へ。
[乙訓地域の空き家担当]
・長岡京市…都市計画課【電話】955-9715
・向日市…公共建物整備課【電話】874-2869
・大山崎町…建設課【電話】956-2101(代表)
○竹やぶ・山林を所有している人は…
大雨や強風で倒れた竹や木、枝が道路をふさがないように、樹木の剪定(せんてい)をお願いします。個人の土地の樹木で事故が発生すると、法律で責任を問われることも。緊急時は道路管理者の判断で伐採や切断をしますが、処理費用などは後日所有者に請求します。
問合せ:道路・河川課 管理係
【電話】955-9522【FAX】951-5410
●「災害時にともに助けあう制度」への登録
高齢者や障がい者など、災害時に1人で避難することが難しい人(災害時要配慮者)が登録し、その情報を避難支援や地域での見守りなどに活用する制度です。
○8月15日(金)までに回答を
今年度新たに対象となる人へ、確認書を送ります。災害時要配慮者として登録するかどうかを回答してください。
対象:要介護3以上の認定を受けた人、障がい者手帳の認定を受けた人など
回答:8月15日(金)までに、下記いずれかで
(1)確認書を返送
(2)確認書のQRから市公式LINEで
*確認書が届かない人も登録できます。詳しくは上記へ。
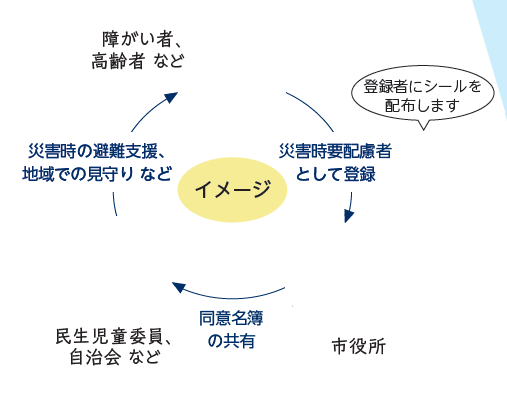
問合せ:地域福祉連携室 地域福祉係
【電話】955-9516【FAX】951-7739
●民間との連携を進めています
災害時に物資供給や運搬を速やかに行うため、市は民間との連携を進めています。昨年12月以降、7つの協定を締結しました。
R6.12月…
フォークリフト等の支援に関する協定(三菱ロジスネクスト株式会社)
R7.2月…
物資調達に関する協定(スギホールディングス株式会社)
物資の供給等に関する協定(株式会社工進)
物資供給に関する協定(NPO法人コメリ災害対策センター)
R7.4月…
一時避難施設としての使用に関する協定(株式会社マツモト)
一時避難施設としての使用に関する協定(上新電機株式会社)
R7.5月…
物資の供給に関する協定(プラス株式会社、株式会社西文堂)
■3.参加して、読んで、楽しく「学ぶ」
●市商工会女性部が開催「防災フェア」
起震車や消防車が集合!消火器の使い方や消防服の着用を体験したり、セミナーやステージを満喫したり、子どもから大人まで楽しめます。キッチンカーや模擬店、能登物産展も。
日時:8月23日(土)午前9時~午後3時
(体験・物販などは午後2時ごろまで)
場所:産業文化会館
問合せ:市商工会 女性部
【電話】951-8029【FAX】958-2473
●消防署の役割や働く人の思いを知る
市の魅力を発信するサイト
「SENSE NAGAOKAKYO(センス ナガオカキョウ)」で関連記事を公開しています。スマホやパソコンで、手軽に読んでみませんか。
問合せ:広報発信課 広報戦略担当
【電話】955-9660【FAX】955-9703
いざという時に自分と周りの人を守るため、日頃から備えておくことが大切です。まずは「知って」、今できることを「準備」して、そして楽しく「学んで」、いつでも落ち着いて行動できるようにしておきましょう。
問合せ:防災・安全推進室 防災・危機管理担当
【電話】955-9661【FAX】951-5410
