- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県足利市
- 広報紙名 : 広報あしかがみ 2025年9月号 No.1612
それぞれの地域が一体となり、防犯の輪を広げていくことが大切です。本市で活躍する、さまざまな立場から地域を見守るボランティアの方の活動をご紹介します。
![]()
■矢場川地区見守り隊として活動する矢場川地区自治会連合会長の岡村さん
矢場川地区見守り隊は、地域に事故や事件がないよう、安全・安心なまちづくりを目指し、児童の登下校の見守りや付き添いなどの見守り活動を実施しています。
▽活動のきっかけ
以前から各町内で子どもたちの見守り活動を実施していましたが、平成29年に見守り活動着(オレンジベスト)を着用した『矢場川地区見守り隊』が発足し、矢場川地区として組織的に活動するようになりました。
▽活動に対する想い
子どもや高齢者のみならず地域住民が事件や事故に巻き込まれないようにするために、地域でできる見守り活動は、重要であると思います。特にオレンジベストの着用は、見守り活動を行う人たちの活動への意識を高めるとともに犯罪への抑止力や周囲への啓発、見える安心につながっていると思います。地域の一員としてできることをこれからも続けていきます。
■足利市地域安全防犯推進協議会矢場川支部長の新井さん
矢場川地区は、高齢者や登下校時の子ども見守り活動を青色回転灯付パトロール車(通称:青パト車)で、毎年130回程度、巡回防犯パトロールを実施しています。
▽活動のきっかけ
矢場川地区の活動起点は、平成17年に女児が被害者となった『今市事件』でした。翌年から、防犯部や交通安全協会を中心に個人の車両に青色回転灯を装備して活動していました。平成28年、当時の矢場川地区自治会連合会長に青パト車を寄贈していただき、今の活動にいたります
▽活動に対する想い
高齢者や子どもたちを巻き込んだ事件・事故が身近な所で起きないためには、地域ぐるみの対応が重要です。
ボランティアの皆さんは、足利警察署の講習などを通して、知識の習得に努め、高齢者や子どもたちを事件・事故から守れるよう日々活動しています。矢場川地区を走る青パト車の光が地域にとって『安全安心のともしび』になるよう活動を継続していきます。
![]()
一般家庭や事業所の方に、『こども見守りのまち』ステッカーを建物の良く見える場所に掲出し、子どもたちが身の危険を感じたときや困ったときに、一時的な避難場所となっていただいています。
日ごろから「おはよう」「気をつけて帰ってね」など声かけにもご協力いただき、地域でのコミュニケーションを大切にしています。
・民間企業との協働
本市と包括連携協定を締結している株式会社セブン-イレブン・ジャパンでは、連携事業として、市内の店舗で同ステッカーの掲出、見守り活動にご協力いただいています。今回、『子ども駆け込み訓練』を実施した店舗のオーナーさんにお話を聞きました。
▽ステッカーを掲示してからの変化
元々、セーフティステーション活動として子どもの見守りを含め、まちの安全・安心の拠点としての機能を持っていましたが、足利市との協働によって、より地域住民に活動が浸透してきています。
特に、行政や警察、学校と協働で実施した不審者遭遇時を想定した駆け込み訓練は、いざという時のためになりました。子どもを保護し、状況の聴取、警察や学校への引き継ぎを実際に経験できたことで、店員の意識も変わったと思います。
▽地域の方へ
コンビニは、皆さまに馴な染じみがあるからこそ駆け込みやすい拠点になると思います。また、常に必ず人がいるというのも強みです。何もないことが一番ですが、有事の際にお役立ちできるようにしたいです。
![]()
地域の方や教員など、114人を少年補導員として委嘱し、街頭補導を実施しています。
街頭補導は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為への指導、有害環境の浄化のほか、子どもたちの見守り活動として『愛のひと声』運動を実施しています。
▽子どもたちとどんな話をしているのか
あいさつを基本とし、「今日は学校楽しかった?」「何をして遊んでいるの?」と学校や今の様子を聞いています。その中で、「そろそろ暗くなるからお家の人が心配する前に帰らないといけないね」などの声かけで啓発をしています。
▽補導員さんの想い
子どもなので間違いや失敗は誰にでもあります。子どものうちにそういう経験を積むことも必要です。しかし、大人になった時に悔いが残る、引き返せなくなるような間違いや失敗をしてほしくないという思いが強くあります。地域の大人として、愛のひと声を通じて子どもを見守っていきたいと思います。
●令和6年度の補導実績実施
日数:118日
従事延べ人数:683人
指導件数:852件
愛のひと声:3,507件
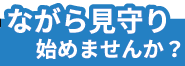
ながら見守りとは…
ウォーキングや犬の散歩、買い物などの日常生活の中で、防犯の視点をもって、地域や子どもたちへの見守りの目を向けることです。
『地域の人の目があること』で防犯効果を高め、犯罪を起こさせない環境づくりへの大きな力となります。できる人が、できるときに、できる範囲で実践してみましょう。
